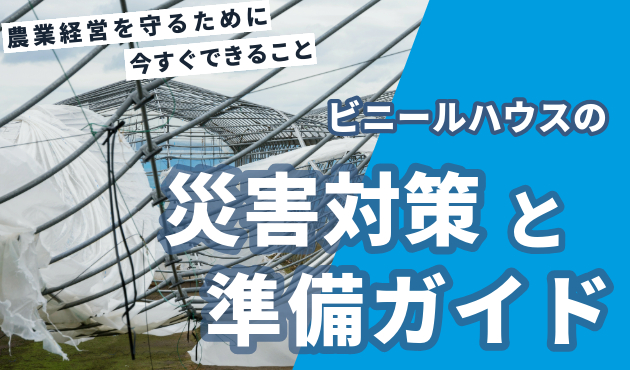
ビニールハウスの災害対策・準備ガイド|農業経営を守るために今すぐできること
執筆者:髙木 憂也
メガデル運営部(株式会社タカミヤ)
はじめに:ビニールハウスの災害リスクとは
日本は地震、台風、豪雪といった自然災害が多発する国であり、農業施設であるビニールハウスも例外ではありません。特にハウスの構造や設置環境によっては、強風や積雪による倒壊リスクが高まります。本記事では、農業従事者が事前に備えるべき災害対策について、信頼できる公的情報を元に解説します。
台風対策:風に強いハウス構造とは
台風による被害で最も多いのが、ビニールの破損や骨組みの倒壊です。農研機構の試算によれば、風速25m/sを超えると通常のビニールハウスでは倒壊リスクが急増します。風に強いハウス構造には以下のような工夫が有効です。
アーチパイプの補強(筋交い追加、ダブルアーチ)
ビニールハウスのアーチパイプは、台風などの強風時に最も大きな負荷がかかる部分です。ここに筋交い(すじかい)を追加することで、パイプ同士の揺れや変形を抑え、全体の剛性を高めることができます。また、アーチ構造を二重にするダブルアーチは、風荷重を分散させる効果があり、強度の面で非常に優れています。これらの補強によって、ハウス全体の耐風性を大きく向上させることができます。
被覆材のしっかりとした固定
ビニールハウスの被覆材(フィルム)は、強風によってめくれたり破れたりしやすい部分です。被覆材が風にあおられると、骨組み全体に無理な力がかかり、最悪の場合は倒壊につながることもあります。そのため、フィルムの張り具合や固定具(止め金具やバンドなど)を定期的に点検・補強し、強風でも緩まないようにしっかりと固定しておくことが重要です。
サイドビニールの巻き上げ(風の通り道を作る)
強風時にハウス内部に風が入り込むと、内部の気圧が上昇して屋根を押し上げる「内圧」により、ハウスの破損リスクが高まります。この内圧を逃がすために有効なのが「サイドビニールの巻き上げ」です。側面のビニールを開けておくことで、風の逃げ道ができ、ハウス内外の気圧差が緩和されます。事前に巻き上げができる構造になっているかを確認しておくと安心です。
豪雪対策:積雪荷重とハウスの耐久性
農研機構の資料によると、ビニールハウスの多くは積雪20~30cmでたわみが生じ、50cmを超えると倒壊の可能性が高くなるとされています。積雪対策として以下が挙げられます
積雪地域向けハウス(雪仕様)への建て替え
雪が多い地域では、通常のビニールハウスでは積雪による倒壊リスクが高まります。そのため、積雪地域向けに設計された「雪仕様」のハウスに建て替えることが有効です。これらのハウスは、骨組みの太さやアーチの間隔、屋根の傾斜などが雪の重みに耐えられるよう強化されています。初期投資は必要ですが、長期的には安心と安定した農業経営につながります。
こまめな雪下ろし
積もった雪をそのままにしておくと、ハウスの天井や骨組みに過剰な負荷がかかり、倒壊や破損の原因になります。特に湿った重い雪や連続した降雪時には注意が必要です。雪が20〜30cm程度積もった段階でこまめに雪下ろしを行うことで、被害を未然に防ぐことができます。また、安全に作業するためには雪下ろし用の道具や足場の確保も重要です。
融雪ヒーターの設置
ハウスの屋根や周囲に融雪ヒーターを設置することで、積もった雪を自動的に溶かし、積雪による被害を軽減できます。特に夜間や人手が足りないときに効果を発揮します。電気式や温水式などさまざまなタイプがあり、地域の気候や設備環境に応じて選定が可能です。省力化と安全性の両立を図るためにも、有効な対策のひとつです。
事前に雪下ろし器具や人員の確保
大雪が予想される前に、雪下ろしに必要な器具(スコップ、除雪用レーキ、安全ベルトなど)や作業に協力してくれる人員の確保を行っておくことが大切です。特に高齢の農家や一人作業が多い場合、近隣の協力体制や外部支援をあらかじめ整えておくと、緊急時に迅速な対応が可能になります。備えを万全にしておくことで、安心して冬を迎えられます。
地震対策:意外と盲点な倒壊リスク
地震は風や雪と異なり突発的に発生します。特に古いハウスや地盤の緩い場所に建てられた施設は注意が必要です。農林水産省では、農業用施設における耐震診断や補強の重要性を指摘しています。地震対策のポイントは以下の通りです。
基礎(杭)の確認と補強
ビニールハウスの安全性を保つためには、地面に打ち込まれている基礎(杭)の状態を定期的に確認し、必要に応じて補強を行うことが重要です。杭がぐらついていたり、腐食や劣化が見られる場合、強風や地震時にハウス全体が傾いたり、倒壊する危険があります。とくに古いハウスや地盤が緩い場所では、しっかりとしたアンカーや補助杭の追加設置が有効です。
骨組みの点検と耐震補強
ハウスの骨組みは、風や地震など外的な力に常にさらされています。定期的にボルトの緩みやサビの発生、パイプの歪みなどを点検し、異常があればすぐに補修や補強を行いましょう。また、交差筋交いや補助フレームの追加などにより耐震性を高めることで、自然災害に強いハウス構造を維持できます。
緊急連絡先・避難計画の周知
地震や台風などの災害時に備え、関係者全員が緊急時の連絡先や避難場所を把握しておくことが大切です。ハウスに常駐するスタッフがいる場合は特に、災害発生時の行動マニュアルを共有しておくと安心です。地域の防災訓練などにも積極的に参加し、実際の行動につなげられる体制を整えておきましょう。
緊急時の備え:日頃の準備がカギ
ハウスの補強に加え、日頃から以下のような備えをしておくことが重要です。農林水産省や全国農業協同組合中央会なども、災害時の備えについて広く啓発を行っています。
- 農業共済や施設保険の加入・見直し
- 停電時の対応(非常用電源、発電機)
- ビニール・資材の予備確保
- 監視カメラや遠隔モニタリング装置の導入
信頼できる施工会社との連携
実際の補修や新設には専門的な知見が必要です。被害が出る前に、施工実績のある専門業者と相談・見積もりを行っておきましょう。緊急対応が可能な業者や、地域に根ざした施工会社を事前に選定しておくことで、災害時の初動が早くなります。

メガデルでは施工実績豊富な地元の施工会社に手数料無料で依頼ができます。
- ご利用は簡単3STEP !!
- ① 会員登録(お名前や住所、連絡先など)
- ② 施工依頼内容を登録・依頼
- ③ 施工会社から応募が届く
まとめ:今からできることを一つずつ
災害は避けられませんが、被害を最小限に抑える備えは可能です。ハウスの状態を点検し、必要な補強や保険の見直し、施工会社との連携を始めておきましょう。「備えあれば憂いなし」。今日からできることを一つずつ実行することが、将来の安心につながります。
出典:農林水産省「施設園芸の台風、大雪等被害防止と早期復旧対策」
出典:農林水産省「災害への備え」
出典:農研機構「果樹茶業研究部門:果樹の災害対策集:1.ハウス栽培における台風対策について知りたい」
