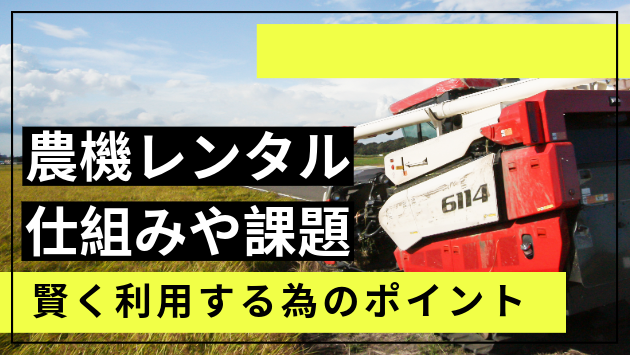
農機レンタルの仕組みや課題、賢く利用する為のポイント
執筆者:髙木 憂也
メガデル運営(株式会社タカミヤ)
農機レンタルとは、農業機械を購入せず必要な期間だけ借りて使えるサービスです。提供主体はさまざまで、JA(農協)や地方自治体、民間の農機レンタル会社などがレンタル事業を行っています。
例えばJAでは組合員向けにトラクターや田植機を日単位で貸し出すケースがあり、自治体でも新規就農者向けに機械貸出制度を設ける例があります。近年はスマートフォンで24時間予約でき、1時間単位で利用可能なシェアリング型サービスも試験導入されるなど、レンタルの形態は多様化しています。
農機レンタル利用の現状と普及状況
日本の稲作農家は、地域や経営環境の違いはありますが、多くが比較的限られた経営面積で作業を行っており、それぞれが自前の農機を保有しているケースが一般的です。高価な機械であっても、作業時期が集中しているため年間の稼働日数はどうしても限られる傾向があります。
一方で農機レンタルやリースの利用率はまだ低く、農林水産省の調査ではレンタル・リース利用率はわずか8.1%に留まっています。これは農繁期の需要集中(ピーク問題)や機械の運搬・整備コスト、故障対応への不安といった課題がボトルネックとなり、レンタル利用の拡大が限定的だからだと分析されています。
もっとも、近年の調査では農業者の過半数が将来的に農機レンタルやサブスク、シェアリングに高い関心を示しており、料金体系の工夫やサービス認知向上次第で普及が進む可能性も指摘されています。
農繁期に必要な主な農機とピーク問題
水稲農家にとって農繁期には特定の農機が不可欠で、代表的なのが田植機とコンバインです。田植えは4月下旬~6月頃、稲刈りは9月中旬~10月上旬に集中し、多くの農家が同時期に利用を希望します。
さらにトラクターや草刈機なども時期ごとに需要が高まり、特に夏~秋にはハンマーナイフモアの予約が殺到することもあります。
農機は年間で使うのは短期間でも、その短期間に地域全体で必要となるため、収穫適期に「在庫が足りず借りられない」という事態が発生します。レンタル業者も特定時期に需要が集中するため機械を十分に配備できず、希望日に利用できないケースが少なくありません。
このピーク問題は農機レンタルの普及を妨げる最大の要因の一つで、農家にとって計画的な営農を狂わせかねない深刻な課題となっています。
ピーク問題の実例と農家の声
農繁期のピーク問題を象徴する実例として、2025年に小泉進次郎農林水産大臣(当時)が「高額なコンバインはリースやレンタルの活用を」と発言した際には、様々な意見がありました。
現場からは「稲刈りの1ヶ月は皆が一斉にコンバインを使う。同じ時期に借りたい農家ばかりで、そんな数の機械を用意できるリース会社なんてあるのか」という批判や疑問が相次ぎました。
実際、ある地域では稲の収穫適期が9月中旬~10月上旬に集中し、その短期間を逃すと米の品質低下や台風被害のリスクが高まります。農家にとって収穫期は絶対にずらせないため、「肝心な時に借りられないくらいなら自前で持つしかない」という切実な現状があります。
また調査でも、「借りたい機械が予約で埋まっていた」ことがレンタルを利用しない理由の上位に挙げられており、繁忙期の機械不足への不安が利用抑制につながっていると報告されています。
農機レンタル利用時の課題とリスク
農繁期の予約難以外にも、農機レンタルにはいくつかの課題とリスクがあります。
まず故障時のリスクです。忙しい収穫作業のさなかに借りたコンバインが故障した場合、すぐ代替機を調達できる保証がなければ作物の被害は避けられません。自前の機械なら事前整備や予備部品の用意もできますが、レンタルでは業者の対応に依存せざるを得ず、「壊れたら収穫が終わる」という心理的不安が付きまといます。
またコスト面では、短期利用には有利でも長期利用になると料金負担が割高になる点がデメリットです。レンタル料金には維持コストや手数料が含まれるため、数週間~1ヶ月を超えるような使用では購入より割高になり得ます。
さらに輸送・段取りの手間も無視できません。大型機械を借りる際は運搬費用が高額になりやすく、往復の運搬料がレンタル料を上回るケースもあります。天候による作業日の変更も融通が利きにくく、返却が遅れれば延滞料金が発生するプレッシャーもあります。
農機レンタルを賢く利用するためのポイント
こうした課題を踏まえ、水稲農家が農機レンタルを効果的に活用するにはいくつかの工夫が有効です。
第一に予約は早めに計画的に行うことです。例えば田植えや稲刈りの時期が分かっているなら、数ヶ月前から予約を始めて日程を押さえておくことが重要です。
第二にレンタル期間に余裕日を設けることもポイントです。天候不順や作業の遅れに備えて前後に余裕を持たせると安心です。収穫期のトラブルに備えて予備日を含める、あるいは予備の機械を検討するのも有効です。
また近隣農家と作業時期を調整するのも効果的です。同じ地区で品種を少しずらしたり、順番を話し合うことで、機械の奪い合いを和らげられます。さらに信頼できるレンタルサービスを選び、故障対応や保険制度を確認することも不可欠です。
地域での農機シェアや自治体の支援制度
ピーク問題への対策や農機購入負担の軽減策として、地域内での機械シェアリングや自治体の支援制度も広がっています。
例えば農村部では昔から集落の農家同士で機械を共同購入・共同利用する「機械利用組合」や、集落営農組織内で大型機械を共有して順番に使う仕組みが取られてきました。
共同利用型では参加農家全員で機械を共有し、各自の作業予定が重ならないよう調整して使うことで、個別に全ての機械を揃えずに済みコストダウンにつなげています。
また農協によっては組合員向けに農機バンク的なサービスを用意し、低料金で貸し出す代わりに地域内で融通し合う体制を取る例もあります。
一方、自治体レベルでも農機シェアリングを支援する取り組みが見られます。たとえば埼玉県さいたま市や京都府亀岡市では、大手農機メーカー(クボタ)と連携した農機シェアリングサービスを展開しており、スマホから簡単予約して燃料・保険込みで1時間単位から利用できる仕組みを全国に先駆けて試験導入しています。
このサービスでは協力農家が機械を保管・管理し、他の一般農家が必要時にシェア利用できるスキームとなっており、地域内の遊休機械を有効活用しながら必要な時に必要なだけ借りられる利便性向上が図られています。
さらに市町村自ら農機を所有して貸し出す制度もあります。例えば山梨県甲府市では市内農家に対してトラクターや管理機などを有料で貸し出す事業を行い、機械の使い方も丁寧に指導してくれます(就農後5年以内の新規就農者なら優先的に借りられる措置もあり)。
長野県坂城町では55馬力トラクターを1時間1000円という低廉な料金で貸すなど、小規模農家でも利用しやすいよう支援する自治体もあります。
このように、地域シェアや自治体のレンタル支援は、個人では所有しきれない高額機械を共同利用でカバーし、“ピーク時でも皆で台数を融通し合う”ことでピーク問題の緩和やコスト削減を狙う取り組みです。
まとめ
高額な農業機械を個人で揃えるのが難しくなっている今日、水稲農家にとって農機レンタルやシェアリングは有力な選択肢です。
レンタルの仕組みは全国規模で整いつつありますが、特に田植え・稲刈り期のピーク問題や故障対応への不安など、乗り越えるべき課題も少なくありません。
しかし、事前の綿密な予約計画や地域内の協力体制、行政・JAの支援策を賢く組み合わせることで、レンタルサービスを効果的に利用する道は拓けます。
機械コストの削減と作業の効率化を両立するために、農機レンタルの現状と課題を正しく理解し、繁忙期を乗り切る賢い機械利用戦略を立てていくことが、これからの個人稲作農家に求められる知恵と言えます。

あなたの理想の農業設備を施工会社へ直接依頼
メガデルはビニールハウスなどの農業設備施工を実際に施工を行う会社に直接依頼できるサービスです。あなたの想い描く営農をサポートします。
会員登録・施工依頼を始める
出典:農機具はレンタルすべき?購入すべき?費用と活用法を徹底解剖 - FARM NAVI(ファームナビ)
出典:貸出農機具 - 甲府市
出典:農機シェアリングサービス事業について - さいたま市
出典:新たな品種・生産技術の開発・保護・普及方針 - 農林水産省
出典:農機レンタルに期待大 導入しやすい料金など 農業支援サービス需要へ適切なアプローチを│農村ニュース
出典:農機具レンタルのメリットとデメリットとは?長期利用なら買取・購入も検討すべき - ウルトラファーム
出典:農機具シェアリング、レンタル、リースの違いを比較!あなたに合った最適な利用方法の選び方 | アグリユース
出典:トラクター、コンバインの農機具レンタルでもっと効率的に!おすすめ業者3選 | アグリユース
出典:集落営農とは? 農業経営や地域の課題を解決する「組織化」 - minorasu
出典:農業人口増加の後押しを目指す!農機のシェアリングは新規就農者を支える - クボタ
出典:【農業支援センター事業】農業機械等の貸出し制度について - 坂城町
