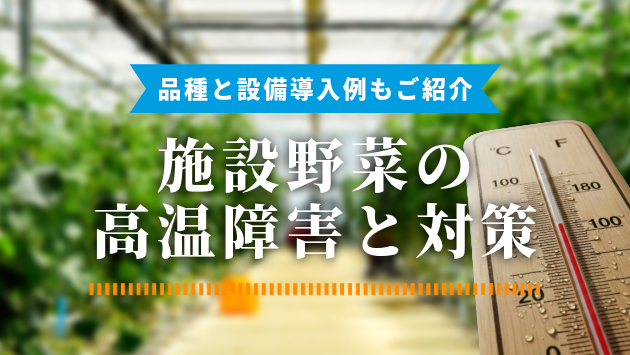
施設野菜の高温障害とその対策(設備導入例)
執筆者:髙木 憂也
メガデル運営(株式会社タカミヤ)
1. 高温障害とは何か(発生メカニズムと影響)
高温障害とは、作物が適温を超える高温環境にさらされることで生育に生理的支障をきたす現象の総称です。
目安として日中の気温が連日35℃以上になると光合成の低下や水分吸収阻害、ホルモン異常などが起こり、生育不良や品質低下につながります。
特に開花や受粉が影響を受けやすく、結実不良による収量減少を招きます。例えばトマトでは高温で花粉の機能が低下し、40℃以上では生育自体が停止します。高温障害が発生すると、収穫量の減少だけでなく外観品質の低下(奇形果・日焼け果など)による商品価値の低下も深刻です。市場での等級低下や価格下落につながり、農家の経営リスクとなります。
近年は夏季の猛暑が常態化しつつあり、高温障害はもはや「異常気象時のみ」の例外ではなく、施設園芸における前提条件として捉える必要があるとの指摘もあります。また、ハウス内作業者にとっても高温多湿環境は熱中症リスクが高く、作業効率の低下要因となります。
2. 主な施設野菜作物における高温障害の症状
作物の種類により高温障害の症状は様々ですが、施設栽培で代表的な野菜について主な例を挙げます。
- トマト(果菜類):高温により落花・受粉不良が起き、着果率が低下します。結実しても果実が肥大しにくく、奇形果や空洞果、尻腐れ果(お尻が黒く腐敗)などの発生が増加します。果実の着色不良や糖度低下も報告され、味・見た目の両面で品質が悪化します。
実際、夏秋期のトマトでは日射による果面温度上昇が放射状裂果(ひび割れ)の原因となり、市販可能な果実割合の低下が確認されています。 - キュウリ(果菜類):高温期には萎れや落花が増え、受粉・着果が不安定になります。実が曲がったりサイズ不揃いになることがあり、酷暑では樹勢が弱って雌花着生率の低下につながります。
果実表面が日焼けして黄緑色や灰白色に変色したり、乾燥を伴うと先端部が細くなる生理障害も発生します。 - ナス(果菜類):高温下では花芽形成不良が起こりやすく、開花数が減少します。結果として落花や着果不足が生じ、収量が落ちます。
着果した果実でも表面に褐変(黒ずみ)や日焼け症状が出やすく、商品価値の低下を招きます。果肉が柔らかくスポンジ状になる障害果も報告されています。 - ピーマン(果菜類):ナス科のピーマンも高温により落花・落果が増え、実が成り疲れ(なり休み)を起こしやすくなります。果実は小ぶりになったり奇形が出やすく、乾燥を伴う高温期にはお尻が黒く腐る尻腐れ果の発生が増加します。
品種によっては真夏でも比較的スタミナを保つものもありますが、一般に酷暑期は収量・品質ともに低下傾向となります。 - レタス(葉菜類):適温より大幅な高温になると生育停滞し、玉レタスでは結球不良や極端に小玉になる小球症が起こります。
葉焼け(葉先が褐色乾燥)や萎れも見られ、最悪の場合枯死する株も出ます。高温下では抽苔(とう立ち)が早まりやすく、収穫適期を迎えないうちに薹が立って品質が大きく低下することもあります。
また、ホウレンソウやリーフレタス等の軟弱野菜では発芽率低下や生育遅延が起こり、規格サイズに達しないB品が増える傾向があります。
以上のように、高温障害は作物によって花や果実、葉への様々な異常となって現れます。症状を早期に察知し、次節以降の対策によって被害を最小化することが重要です。
3. 高温障害に強い品種の例
近年、高温期でも安定生産が可能な耐暑性品種の育成が各地で進められています。
品種選定は高温リスク軽減の基本対策の一つであり、生育適温の高い品種や高温下での着果安定性に優れた品種を選ぶことで被害を抑えることが可能です。
主な施設野菜について、高温に強い品種の一例を挙げます。
- トマト:「桃太郎ワンダー」や「TY千果」などは、高温期でも着果が安定し裂果や病害に強い品種として推奨されています。
これらは従来夏秋期に問題となりがちな果実の割れや着果不良を軽減でき、酷暑下でも品質の高い果実を維持しやすいとされています。
また農研機構や大学では、40℃以上の高温でも生育可能な接ぎ木トマト(高温耐性台木の活用)など新技術の開発も進んでいます。 - キュウリ:近年育成された例として露地抑制栽培向け品種「クロスター」があります。
真夏の高温環境に耐え、生育後半まで樹勢を維持できるため果実の揃いが良く、高い秀品率が期待できる品種です。
このような耐暑性品種を使えば、従来は栽培が難しかった盛夏期の収量安定が見込めます。 - ナス:各地の試験場で高温下でも花芽形成や着果が安定する新品種の開発・実証が進められています。
具体的な品種名は地域によりますが、高温期に樹勢が落ちにくく連続着果性の高い品種が選抜されています。
群馬県ではこうしたナス新品種の現地試験を行っており、耐暑性品種の普及が期待されています。 - ピーマン:「京波(きょうなみ)」は耐暑性に優れた中型ピーマン品種で、夏場の高温下でも草勢が維持しやすく実付きが安定します。
果実も肉厚で乾燥期の尻腐れや裂果に強い特長があります。
この品種は高温期になりやすい生理障害を抑え、盛夏でも収量を確保しやすいことから家庭菜園からプロ農家まで幅広く注目されています。 - レタス:「タフV」は夏季の高温期栽培向けに開発された玉レタス品種で、その名の通り耐暑性抜群で病気にも強いことが特徴です。
高温期でも玉肥大と結球が安定し、抽苔が遅い極晩抽性(とう立ちしにくい)を持つため、夏どり作型で秀品率の高い収穫が期待できます。
その他「パトリオット」「エクシード」など各種苗会社から耐暑性品種が販売されており、地域の作型に合わせて選ぶことが重要です。
以上のように、「品種選び」は高温対策の第一歩です。導入コストも種苗代程度で済むため、これから就農する方や作型転換を図る農家にとって取り組みやすい対策と言えます。各地の普及センターや種苗会社の情報を参考に、自圃場の条件に適した耐暑性品種を選定するとよいでしょう。
4. 高温対策として導入されている主な設備
高温障害を防ぐには、ハウス内環境そのものを冷涼化・安定化する設備導入が効果的です。ここでは、施設園芸で広く導入されている主な高温対策設備について、その概要とポイントを紹介します。
(1)遮熱資材の導入: 太陽光による過剰な熱侵入を抑えるために、遮光ネット・遮熱シートが多用されています。ハウス外部に被覆するアルミ蒸着の反射シートや白色ネットは赤外線を反射し、ハウス内の気温や作物表面温度を下げる効果があります。
外張り(屋根上)に設置するタイプは内部設置よりも熱を入る前に遮断できるため冷却効果が大きく、近年は軽量で展張しやすい白色ネット資材(例:「ふあふあホワイトプラス™」など)も開発されています。
一方、ハウス内部に巻き上げカーテン式で設置する遮光ネットもあり、開閉操作が容易で冬季の保温資材と兼用できるメリットがあります。
さらに、夏季のみ屋根ビニールに塗布して赤外線を遮る遮熱塗料も利用されています。必要なくなれば洗い落とせるため手軽で、果実の日焼け防止に有効です。遮熱資材の導入によってハウス内温度を数℃下げ、品質・収量を守る効果が期待できます。(2)換気装置の強化: ハウス内の熱気を排出し外気と入れ替える換気は、最も基本的な高温対策です。近年は従来より開口面積の大きい天窓や妻面(ハウス端部)換気窓を設ける改造が進んでいます。
例えば妻面上部に大型の換気窓(通称「ツマカン」)を増設すると、ハウス頂部に滞留する熱気を効率良く逃がせ、内部温度の上昇抑制に効果的です。
また、側面の換気も1段巻き上げから2段階巻き上げ式に変更することで開口部が拡大し通風が向上します。加えて、換気扇(排熱ファン)や循環扇の設置により強制的に空気を動かすことも有効です。
妻面に大径ファンを取り付ければ高温多湿の空気を強力に排出でき、屋内上部に向けたサーキュレーションファンで対流を起こせば温度ムラを解消し均一環境につながります。
実際、天窓直下に上向き扇風機を置き強制排熱する手法は、屋根付近に溜まる熱気を素早く外に押し出す効果が確認されています。このような換気装置の強化により、ハウス内気温を外気温に近づけることが高温障害軽減に寄与します。(3)冷房・ミスト冷却設備: 電力や水を用いて積極的に温度を下げる装置も普及し始めています。代表的なのがミスト(霧)冷房で、微細な水粒を噴霧し水の気化熱で空気を冷やす仕組みです。
一般的なスプリンクラー式の散水ミストはコストが安価ですが植物体を濡らすため病害発生や気孔閉鎖のリスクがあります。一方、高圧細霧装置(ドライミスト)は10~40ミクロンほどの非常に細かい霧を空中で蒸発させることで、作物や床を濡らさずに効率的冷却できます。
初期費用は高めですが、作物への負荷が少ないため近年注目され問い合わせ件数が前年の5倍以上に増えているとの報告もあります。加えて、ハウス壁面に濡れたパッドを設置し送風機で外気を強制吸気するパッド&ファン方式もありますが、日本の高温多湿環境では効果が出にくく導入例は少ないです。
もう一つ簡便な冷却策として、屋根散水があります。屋根ビニール外面に散水チューブで定期的に水をかけ、蒸発によって屋根表面を冷却する方法で、ハウス内を濡らさず安価に導入できます。
大量の水が必要という条件はありますが、タイマー制御で「2分散水・8分停止」を繰り返す実験では気温を最大3.5℃低下させたデータがあり、水源が確保できる地域では再評価されています。
積極冷房としては、農業用エアコン(冷暖房機)の導入事例も現れています。住宅用エアコンと同様にヒートポンプで熱交換し冷風を出す仕組みで、夜間に運転してハウス温度を下げるなどの活用がされています。
ただしビニールハウスは断熱性が低く日射の影響も大きいため、遮熱資材や断熱対策と組み合わせないと冷房効率が悪い点に注意が必要です。
地中熱を利用した地下水クーリング(井戸水やチラーで冷水を循環)による空調技術も開発されています。これは地下水温の年較差が小さいことを利用し、冷えた水で空気を冷却してから温まった水を地下に戻す循環式で、省エネな冷房として期待されています。(4)断熱パネル・多重被覆: ハウス自体の断熱性を高め、外気の熱影響を減らす手法も重要です。具体的には、屋根や側面を二重被覆にして間に空気層を設けたり、発泡断熱材パネルを一部に用いる方法があります。
二重被覆はビニールフィルムを二層にして空気の層で断熱するもので、温度上昇抑制に一定の効果があります。例えば外張りフィルム上に間隔を空けてもう一枚フィルムを被覆すると、間の空気層で断熱効果が高まり夏季の温度上昇を抑えることができます。
また、ハウス内部の二重カーテン(内張り+遮熱カーテン)によって遮熱と保温を両立する方法もあります。遮熱ネットと保温カーテンの二層を使えば夏は遮熱・冬は保温が可能で、通年で環境安定化に寄与します。
さらに、ヤンマー社が開発した高温対策装置「断熱送風栽培槽DN-1」のように、発泡断熱材で作られた栽培ベンチ内に空調機からの冷風を送り込み、イチゴの株元(クラウン)を直接冷やす先進的な機械も登場しています。
この装置では冷風による局所冷却に加え、必要に応じ温風やCO₂施用も同時に行えるとのことで、従来は難しかった夏場イチゴ栽培を可能にする試みとして注目されています。
以上のように、遮熱・換気・冷却・断熱の多角的な設備導入によって、ハウス内の温度ストレスを和らげることができます。導入コストや適用範囲は設備によって様々ですが、次節でその費用対効果や支援策について解説します。
5. 導入コストや効果(生産性・品質・収量の改善)
高温対策設備の導入には初期投資やランニングコストが伴いますが、その効果として収量維持・品質向上が得られる可能性があります。ここでは費用対効果の観点から主な対策のメリットを述べます。
●低コスト対策の効果: 遮光ネットや屋根散水など比較的安価な資材でも、適切に活用すれば大きな効果が報告されています。
例えば熊本県農業研究センターの試験では、赤外線カット資材(高性能遮熱ネット)をハウス外に終日展張した区画で、遮熱なし区画に比べ果実表面温度が平均5.7℃低下し、トマトの放射状裂果の発生が顕著に減少しました。
その結果、市販可能な果実割合が最も高くなり、可販収量の増加につながっています。
同様に岡山県の研究では、夏季に屋根ビニールへ遮熱塗料(レディヒート)を塗布することでトマト果実表面温度が2.9~3.3℃低下し、裂果の抑制と販売果実の増加が確認されました。
さらに、高知大学の実験ではナス栽培で熱線反射フィルム(遮熱フィルム)を使用したところ、地温を平均1.9℃低減し、障害果の発生が抑制され一部品種で総収量が増加しました。
パプリカでも同様に遮熱フィルム区画で総収量増加とひび割れ果の低減が得られています。
軟弱野菜においても、住友金属鉱山開発の近赤外線吸収資材「青天張(あおてんばり)」を導入した農家では、従来の遮光シート使用時より発芽率が安定し、収量が約1.5倍に増加する成果が報告されています。以上から、遮熱資材の投資は品質ロス防止と収量確保に十分見合う効果を発揮しうると言えます。
ネットや塗料はハウス規模にもよりますが数万円程度から導入可能で、猛暑年の減収リスクを考えればコストパフォーマンスは高いでしょう。
●換気・環境制御の効果: 換気強化やICT環境制御装置は中程度の投資となりますが、省力化と収量安定をもたらします。
千葉県旭市のある先進的ミニトマト農家(石井さん)は、ハウス両妻面に外気導入システム「コリドー(空調室)」を施工し、夏場でも24時間平均気温を約26℃に保つ環境を実現しています。
外気を積極的にハウス内に送り込むことで、猛暑日でも日中28℃前後の制御が可能となり、高温障害による着果不良を抑制できています。
石井さんは反収40トンという高収量を目指しており、環境制御導入後も安定した栽培を継続できているとのことです。
このように、温度・換気を自動制御するシステムの効果として収量と品質の平準化、ひいては経営安定に寄与する点は大きなメリットです。ただし導入費用は数百万円規模になるケースもあり、初期投資回収までに時間がかかります。そのため国や自治体の補助事業を活用し導入する例が増えています。

あなたの理想の農業設備を施工会社へ直接依頼
メガデルはビニールハウスなどの農業設備施工を実際に施工を行う会社に直接依頼できるサービスです。あなたの想い描く営農をサポートします。
会員登録・施工依頼を始める
出典:高温障害から野菜を守る!効果的な対策法とは? - 農業屋
出典:〖トマトの高温障害〗症状・対策を解説!酷暑でも収量を落とさない栽培方法 | minorasu(ミノラス)
出典:農業用遮熱ネットで夏のハウス栽培を対策!高温対策の効果と選び方 | minorasu(ミノラス)
出典:施設園芸・植物工場展〖GPEC2024〗で見つけたハウスの暑さ対策資材! | 施設園芸.com
