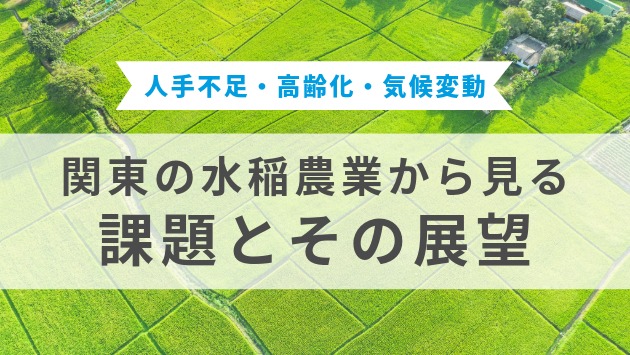
関東の水稲農業から見る課題とその展望
執筆者:髙木 憂也
メガデル運営(株式会社タカミヤ)
人手不足と高齢化による労働力危機
関東地域の稲作農家では深刻な人手不足が続いています。農業の担い手となる基幹的農業従事者数は、2000年の約64.2万人から2023年には31.5万人へと半減し、その約7割以上が65歳以上という超高齢化状態です。
特に田植えや稲刈りといった繁忙期の労働力確保は困難で、「作りたくても作れない、あるいは人手が足りない」という状況が深刻化しています。例えば関東周辺で始まった2025年産米の早場米収穫でも、異例の猛暑と水不足により高温障害や病害が頻発し、需要期の人手確保と対応に追われています。
高齢の農家にとって重労働の田植え・収穫作業は負担が大きく、地域ぐるみの助っ人や外国人技能実習生に頼らざるを得ないケースも出ています。今後、ロボット技術やドローンを活用した省力化(スマート農業)の導入が、人手不足緩和の鍵として期待されています。
後継者不足と新規就農の壁
農家の高齢化に伴い後継者不足も顕在化しています。各自治体が2023年3月に策定した地域計画の集計によれば、全国の農地の約32.8%で将来の後継者が未定となっており、関東地方ではその比率が49.4%と半数近くに達しました。つまり関東管内の水田の約2枚に1枚は、このままでは耕作を引き継ぐ人がいない計算です。
この問題は小規模な家族経営だけでなく大規模経営にも共通しており、15ヘクタール以上の大規模経営体の約4割で後継者が確保されていない実態も明らかになっています。
新規就農者の絶対数が不足する一方で、農地取得資金や機械導入資金のハードルも高く、若者が稲作経営を始めるには多くの課題があります。例えば、水稲農家に必要なトラクター等の法定耐用年数は7年と短く、400万円の投資なら年当たり約57万円もの減価償却費が発生する計算で、小規模経営では初期投資の回収に時間がかかりすぎるという指摘があります。
こうした経営継承の困難さを受けて、国や自治体は地域計画(人・農地プラン)による担い手農家への農地集積や、新規就農者への交付金制度など後継者確保策を急いでいます。
実際、国は49歳以下の新規就農者に対し経営開始直後の生活支援資金を最長3年間・年最大150万円給付し、機械設備導入には最大1000万円(国と都道府県の補助)を支援する制度を設けるなど、新規就農の壁を下げる取り組みを進めています。
収益性低下と米価の変動リスク
日本人のコメ消費量減少に伴う需要縮小や長年のコメ政策の影響で、稲作農家の収益性は低下傾向にありました。近年は市場原理でコメ価格が推移するため、生産過剰になると米価が下落して農家所得を圧迫します。
反対に2022年産米の不作(高温や天候不順の影響)により“令和の米騒動”とも呼ばれる品薄・価格高騰が発生し、2024年秋のコメ卸売価格は全銘柄平均で60kgあたり2万2700円と過去最高値を記録しました。
米価上昇自体は農家に追い風ですが、その恩恵を十分享受できるのは販売数量を確保できる大規模経営が中心であり、小規模農家では売上増に直結しにくい面があります。また近年の燃料費・肥料代の高騰など生産コストの上昇が収益を圧迫しています。
ある調査では7割以上の稲作法人が前年より生産コストが1.1~1.5倍に増加したと回答しており、資材・燃料価格の高騰による構造的コスト増が浮き彫りになっています。
米価が上がっても肥料や機械経費も軒並み値上がりしていては、農家の手取りは思うように増えません。この調査では令和6年産米について約8割の法人が増益を見込む一方で、「設備コストの高さ」「人手不足」「生産コスト高騰」「米価暴落のリスク」といった要因が今後の不安要素として挙げられています。
特に農業機械の取得費用が高すぎるとの回答が最多で、生産資材費の高騰や労働力不足と並び、米価変動と収支の不安定さが経営の重荷となっています。こうした収益環境を安定させるため、政府は収入保険制度の普及を進め、農家が天候不良や価格下落で収入減少した際に補填を受けられるセーフティネットを整備しています。
またJA全農による市場調整やミニマムアクセス米の活用、備蓄米の放出基準の見直し議論など、需給安定策も講じられています。もっともコメ需給の中長期見通し自体は年々10万トン規模で主食用米需要が減少する厳しい状況であり、米余りによる価格下落リスクと隣り合わせである点には引き続き注意が必要です。
水田の維持管理:耕作放棄地と機械更新負担
高齢化と後継者不足の結果、耕作放棄地の増加も大きな課題です。全国の耕作放棄地面積は約38.6万ヘクタールにも達し、これは一つの県(埼玉県や滋賀県)の面積に匹敵すると報告されています。関東地方でも都市近郊を中心に、水田が工作放棄地化して雑草や藪に覆われる例が見られます。
水田が管理放棄されると、用水路や農道の維持にも支障が出て地域全体の農業基盤が劣化してしまいます。また、農業機械の老朽化と更新負担も農家に重くのしかかっています。とりわけ小規模農家では高額なコンバインや田植機の買い替え費用を捻出しづらく、長年使い続けた旧式機械が故障するとそのまま離農に至るケースもあります。
実際、日本の農機具市場はすでに普及が一巡した成熟期にあり、多くの農家が「旧型農機の更新」か「体力の限界による廃業」かの選択を迫られているとの指摘があります。稲作では複数の大型機械が必要ですが、一度に全て更新するのは困難なため、機械更新のたびに経営を縮小したりリタイアを検討する高齢農家も少なくありません。
こうした事態を防ぐため、近年は農家が共同で機械を利用するオペレーション・グループや、自治体の支援によるレンタル機械サービス等も模索されています。
また、農業法人や集落営農組織への農地集約が進めば、効率化による生産コスト低下とともに機械の共同利用や更新投資の効率化が期待できます。
現に関東各地でも集落営農による受託作業で地域の水田を維持管理する事例が増えており、高齢農家から機械作業を請け負うカスタム業者・JA子会社の存在感も増しています。今後も機械更新への公的助成やリース制度の充実、農地集約の加速によって、水田の維持管理負担を軽減していくことが急務です。
気候変動がもたらす生産リスク
近年、気候変動の影響が関東の稲作を直撃しつつあります。夏季の気温上昇に伴い、登熟期の高温によるコメの品質低下(白未熟米の発生など)が大きな問題となっています。関東農政局によれば、近年は各県で高温障害対策技術の開発や高温に強い品種の導入が進められているものの、高温多湿な気候によるコメ品質の低下傾向は無視できません。
実際に2025年産米でも、猛暑と少雨の影響で千葉県香取市の水田では玄米が黒変する“焼け米”や穂いもち病の被害が昨年の2倍規模に拡大し、一部で収量・品質低下が避けられませんでした。
生産者からは「被害は全体の2割程度にも上った」との声もあり、高温・干ばつが稲作経営にもたらすリスクが露わになっています。さらに、大型台風や豪雨による水害も無視できません。台風15号(2019年9月)や台風19号(同年10月、東日本台風)では関東各地の河川が氾濫し、水戸市や佐野市、那珂市など広範囲で水田が浸水・埋没する甚大な被害が発生しました。
農林水産省の集計では、台風19号による農業被害額は全国で616億円を超え、うち農作物被害が85億円以上(主に水稲や果樹)に上りました。関東平野は大河川の下流域が多く、水田地帯も低地に広がるため、ひとたび堤防決壊や内水氾濫が起これば甚大な農地被害につながります。
温暖化で台風の勢力が衰えにくくなり北上傾向が強まる中、関東でも従来以上に台風・豪雨災害への備えが必要です。気候変動に打ち勝つには、耐暑性品種への転換や直播栽培による作期分散、用水の効率的な確保策など気象リスクを織り込んだ営農体系の再構築が求められています。
さらに、異常気象による不作時には米価高騰・品薄となるリスクもあるため、平時からの備蓄米の充実や産地間連携も課題と言えます。
小規模農家と大規模法人の動向:違いと共通課題
関東地方の稲作構造を見ると、小規模家族経営から大規模農業法人まで多様な経営体が混在しています。
その違いとして、大規模経営は広い農地と資本力を背景に生産コストの削減や新技術導入に積極的であり、米価上昇局面では作付拡大による収益拡大を図る傾向があります。実際、全国の農業法人調査でも「今後5年で作付面積を1.1~1.5倍に増やす」計画の法人が約半数に上りました[22]。
関東でも法人経営が進む茨城県や栃木県などでは、大区画圃場で大型機械を駆使し、高収益を上げる先進事例が出ています。一方、小規模農家は平均経営面積が狭く、高齢の家族労働に依存するケースが多いため、大規模ほど生産効率を高められず経営改善に苦慮しています。
都市近郊では兼業農家として農閑期は別の職業収入で支える例も多く、「稼げる農業」への転換が大きな課題です。ただし規模の大小を問わず、前述した人手不足や気候変動リスク、資材高騰といった課題は共通しています。
興味深いことに、大規模経営でも後継者不在率が4割に達するように、事業承継という点では規模を超えて共通の悩みが存在します。
また、中小農家と大規模法人が地域内で共存し助け合う動きも見られます。例えば、集落営農的に小規模農家の田植え・収穫を大規模法人が受託することで双方にメリットを出す協業モデルや、JAが仲介して小規模農家のコメを大規模施設で一括乾燥調製する仕組みづくりなどです。
共通課題の解決なくして規模拡大も持続不能であるとの認識から、大規模・小規模の垣根を越えた地域ぐるみの連携が関東でも進み始めています。小規模農家の強みであるきめ細かな土地管理と、大規模経営の効率的生産を組み合わせることで、地域全体の水田農業を維持発展させる展望が開けるでしょう。
政府・自治体・JAによる支援策と今後の展望
以上の課題に対し、政府や自治体、農協(JA)も様々な支援策を講じています。人手不足への対応としては、スマート農業技術の普及支援があります。関東農政局では管内39地区で自動運転機械やICTを活用した実証プロジェクトを展開し、生産性向上と省力化の成果を横展開しています。
これにより、省力化技術や新品種の導入について現場レベルでノウハウが蓄積されつつあります。また後継者不足への対策として、国は農業次世代人材投資資金(経営開始型)による若手就農者の定着支援を継続中です。具体的には49歳以下の新規就農者に最長3年間・年間150万円の交付金を支給し、就農直後の経営安定を下支えしています。
加えて、経営発展支援事業により機械・施設等の導入費用の1/2を国が補助する制度も創設され、都道府県と合わせて最大1000万円までの投資支援が受けられます。この制度によって、高額な農業機械の更新や新品種導入など初期投資へのハードルを下げ、経営継承を後押ししています。
融資面でも、日本政策金融公庫が青年等就農資金(無利子融資、最大3700万円)を提供し、返済据置期間を長めに設定することで若手の設備投資を促しています。
耕作放棄地対策としては、各県が農地中間管理機構(いわゆる農地バンク)を通じて遊休農地の集積・貸し出しを進めています。使われていない水田を借り受けて耕作したり、新規参入希望者にリースする仕組みで、関東でも茨城県などを中心に農地バンクが成果を上げています。
自治体独自の支援策も多様です。例えば千葉県は高性能農業機械のリース導入補助や、独自の担い手育成研修制度を設けており、埼玉県でも地域担い手育成のための交付金や農作業ヘルパー派遣事業を行っています。
JAグループもまた重要な支援主体です。JAは経営指導や営農相談を通じて高齢農家の経営をサポートし、必要に応じて集団作業の組織化や機械の共同利用を仲介しています。また、JA全農は市場動向を踏まえて生産者に適正な仮渡金(概算金)を提示し、安定した米販売を支えるとともに、需要に応じた作付け転換(例えば主食用米から飼料用米への転作)には助成金を通じて誘導を図っています。
近年問題となった飼料用米助成の縮減に関しては、生産現場から「補助金がなくなれば水田を維持できない」との声も強く、引き続き財政支援と水田有効活用策のバランスを探る必要があります。
今後の展望として、関東の水稲農業が持続的に発展していくためには、「人・物・技術」の各方面での改革が不可欠です。人的側面では、新規就農者や地域の農業法人への農地集約をさらに進め、経営規模拡大と労働生産性の向上を図ることが重要です。
物的側面では、老朽化した農業インフラや機械の更新を計画的に支援し、農家の負担を軽減するとともに、スマート農機や耐候性品種への投資を促す政策が求められます。技術面では、気候変動に対応できる栽培法(直播や中干しの工夫、リモートセンシングによる水管理等)の確立や、高温耐性・病害抵抗性に優れた新品種の育成・普及が期待されます。
こうした取り組みを支える制度設計(収入保険のさらなる拡充や環境直接支払いの検討など)も含め、官民一体で改革を進めることで、関東圏の水稲農家・農業法人は逆風を乗り越えられるはずです。課題は山積していますが、各種データや現場の声に基づいて的確に課題を整理し、利用可能な支援策を活用していけば、関東の水田はこれからも持続可能な形で次世代へ引き継がれていくでしょう。

あなたの理想の農業設備を施工会社へ直接依頼
メガデルはビニールハウスなどの農業設備施工を実際に施工を行う会社に直接依頼できるサービスです。あなたの想い描く営農をサポートします。
会員登録・施工依頼を始めるあわせて読みたい記事
- 施設野菜の高温障害とその対策(設備導入例)
- 農家の夏作業をラクにする!暑さ対策便利グッズをご紹介
- ぶどう棚の設置費用と相場感|費用を抑えるコツも紹介
- ハウス栽培の初期費用はいくら?設備投資と収益回収までの目安や作物ごとの特徴を解説
- 「ビニールハウスのフィルム張替え費用相場|張替え方法と耐用年数・減価償却も解説」
- 農地の賃借は相対から農地中間管理事業を介した賃借に移行~令和7年4月より~
- 農業の世代交代を支援する新たな取り組み 親元・第三者継承型の就農支援策
- 茨城の農業をご紹介|農業産出額や地域ごとの特色
- 台風シーズンに備えるビニールハウス補強・修繕チェックリスト
- 農機レンタルの仕組みや課題、賢く利用する為のポイント
- 農家が始める“加工品づくり”|6次産業化のリアルな収支と工夫
出典:農林水産省 関東農政局|関東食料・農業・農村をめぐる事情(令和6年版)
出典:SMART AGRI|田植えをしないお米づくりが当たり前に? 直播栽培の新常識
出典:テレビ朝日ニュース|高温障害で“焼け米”2倍に 関東でも新米収穫始まる
出典:千葉日報オンライン|農地の32%で後継者未定(2025年4月17日)
出典:JAcom 農業協同組合新聞|大規模経営体4割で後継者なし 米不足議論に(2024年8月)
出典:三菱総合研究所|小規模コメ農家の経営継承は危機的状況(2023年7月)
出典:全国新規就農相談センター|国の新規就農支援施策
出典:日本農業法人協会|米価上昇も生産コストが課題に(2025年6月)
出典:農林水産省|増加する耕作放棄地(参考資料)
出典:マイナビ農業|農業の大規模化・機械化の先にある現場課題
出典:関東農政局|関東の水稲
出典:JAcom 農業協同組合新聞|台風19号の農業被害は30都府県で600億円超(2019年10月)
出典:AGRI JOURNAL|温暖化に対抗!農研機構の注目コメ品種「にじのきらめき」
出典:J-FRA|飼料用米は水田を守る要「水活から除外」の財政審建議に対する見解(PDF)
